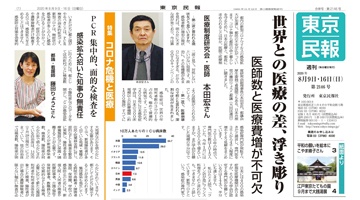新型コロナウイルスの感染拡大は、日本と世界の抱えるさまざまな問題をあぶりだし、社会のあり方を問うています。今から約100年前、明治期の日本にはペストが流行しました。当時を生きた、夏目漱石、石川啄木の文章から見えることを、憲法に基づく民主的な吟詠の会として活動する新興吟詠会本部事務局長の園部道佳さんの寄稿で紹介します。
◇ ◇
コロナ禍と豪雨、相次ぐ自然災害の中、人間が自然に鋭く問われる状況が浮き彫りなってきています。日本の資本主義の発展を切り開いた明治。その渦中、日本を代表する文豪・漱石と、歌人・啄木はどのような日本への想いをもっていたのでしょうか。

漱石とペストの流行
1899年(明治32年)、日本でのペスト流行の中、漱石は、明治維新後の日本を見つめていました。
「吾輩は猫である」では、流行の元凶である鼠捕りが奨励され、交番で一円五〇銭で買うてもらったこと、猫の主人・苦沙弥先生が、感染症で痘痕面であったことが書かれています。
そして、激しく移り変わる「文明開化の明治日本」を「開化が進めば進むほど競争がますます劇しくなって生活はいよいよ困難になる」(「現代日本の開化」)、「焦慮に焦慮て、汗を流したり呼息を切らしたりする。恐るべき神経衰弱はペストより劇しき病毒を社会に植え付けつつある」(「マードック先生の『日本歴史』」)と鋭い眼差しでみています。
さらに、「三四郎」では、日露戦争後の日本について「滅びるね」と語っています。
江戸末期から大正5年(1916年)まで、明治時代を生き抜いた漱石の死後、30年後には、軍国日本は太平洋戦争で「滅び」、「主権在民」の平和憲法を生み出しました。
漢詩を生きがいとした漱石は、「総決算の詩」と言われている「無題」を死直前に創り、「真実の道は、ひっそりとしてかすかで、手の届かない彼方にある」「ひとり空中に浮かんで白雲の歌を歌っている」と思いを詠いました。

啄木の人間への警告
新型コロナをはじめ、新たな感染症が次々と出現している要因に、人間による生態系への無秩序な進出と、熱帯雨林の破壊などの環境破壊が指摘されます。
啄木は、百年前の随想「猿と人と森」で、「人間はいつの時代も木々を倒し、山削り、川を埋めて、平な道路を作ってきた。だが、その道は天国に通ずる道ではなくて、地獄の門に行く道なのだ」と、サルは白雲落日の山に行ってしまった(盛岡中学交友誌の「林中の譚」)と記し、自然を破壊していく人間へのサルの警告を発しています。
啄木は、杜甫などの漢詩の本をよく読み、大逆事件や朝鮮併合、日本にも滞在していた魯迅(小説家、思想家)や秋瑾(詩人、女性革命家)の革命運動にも大きな関心をもち、特に惨殺された秋謹女史を想う詩を詠っています。文芸誌「明星7号」(明治41年)には、「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹と戯る」「血を見ずば飽くを知らざる獣の本性をも神を崇めむ」を「石破集」として百余首の短歌を発表、治安警察法のもと、整理、集大成して「一握の砂」として出版しました。
漱石、啄木の中にある「白雲」とは、漢詩では、俗世間に対しての理想郷をあらわしています。
求められる新しい世とは、人間、自然の尊厳を明記した「憲法の世」ではないでしょうか。いま、私たち新興吟詠会は、コロナ禍、政権私物化のアベ政権の「二つの病原」を正す「療治は憲法の力」と、創作詩を全国で吟詠しています。